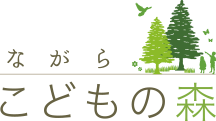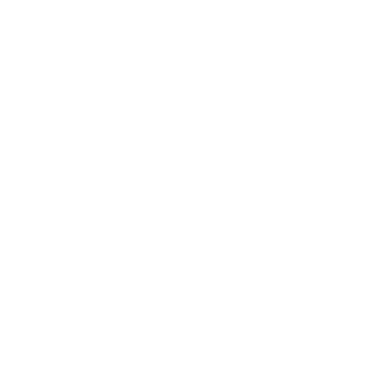2021年2月 森のたより
雪が多い冬のようですが、日差しは意外と暖かく、子どもたちの園庭遊びも毎日楽しそうです。
「光るどろだんご」が子どもの遊びに登場したのいつ頃でしたでしょう。20年以上前になると思います。それまでも「どろだんご」は砂場遊びの定番でしたが、「光る!」と形容されているので興味がわき、僕自身も挑戦。なるほど。確かに「光るどろだんご」が出来上がりました。
その「どろだんご」は今も持っていて、記念品のような存在になっています。(下の写真)

「どろだんご」は、もちろん「どろ」で作ります。なかなかいい泥がないのですが畑土に砂を混ぜたのがいいですね。どんな土がよかったかなとインターネットで検索したら・・・・なんとたくさんの「泥団子つくり」が紹介されていました。要するに、次第に細かな土をかけて土の粒子のすき間を埋めていけばよいわけです。
この乾いた砂に手を入れて引き上げたときに掌についてくるパウダーのような砂を集めていた時に、どこかでこの粉を見たのを思い出し、そういえば粉絵具のようだと・・・・・そこで粉絵具を使うこととなり、さらに絵の具の色を変えて、ストッキングで磨き出来上がりました。
20年以上経過しますが、今でも光は失われず、壊れもしません。なんとたくましいものです。