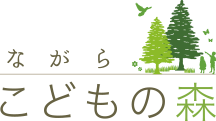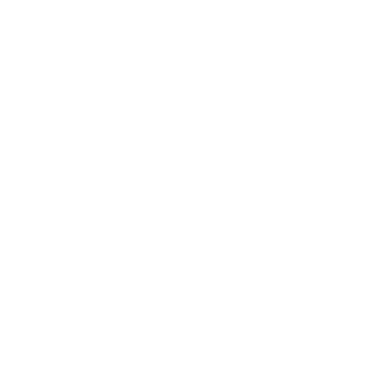2022年1月 森のたより
新年あけましておめでとうございます
西の山々はすっかり白くなってしまいました。あわただしい年末の雪には閉口しました。しかし、年が改まると、なんだか昨日と同じ一日が違う日のように感じます。毎年、新年を迎えているのですが、令和4年、2022年の年を迎えるのは初めてです。こういう新鮮な気持ち、心持ちを大切にしたいと思います。
「いないいないばあ」は童心社から松谷みよ子文、瀬川康男絵で「まつたにみよこあかちゃんの本」として昭和42年に出版されました。ブルーナの「うさこちゃんシリーズ」から数年経ていましたが、最初の日本の赤ちゃん絵本の傑作です。
「いないいないばあ」という遊びは親子がいつでもどこでも遊べるとっても素敵な遊びです。顔がすべて隠れてしまうと赤ちゃんは怖がって泣いてしまいます。園ではオーガンジーを使っています。かすかに見える・・・というのが安心なんですね。手で顔を覆うのは全てを覆い隠すことができないことが、楽しさの秘訣なんです。なんでもない言葉のやり取りがこどもの感性を育てていきます。この絵本が出版されたときには賛否両論あったということです。本来大人と赤ちゃんの遊びだからそのことをもっと大切にすべきだ。わざわざ絵本にするのはいかがなものかという反対論と、赤ちゃんが大好きな遊びを絵本で再現することで絵本に親しみを持つことができるという賛成論。
皆さんはどう思いますか?僕は1冊の赤ちゃん絵本が出版されただけで、そのように議論が起こることのほうがすごいと思ってしまいます。