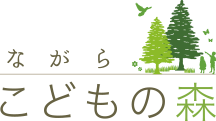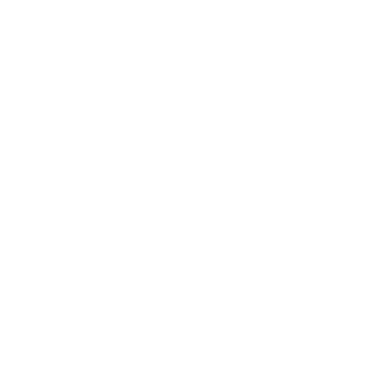ツブラジイのふもとで
心地よい秋の風がうれしい頃になりました。秋の森フェスも終わりました。お子様の様子はいかがだったでしょう。昨年までは、コロナ禍のなかでの森フェスということで、何か物足りないと感じておられる方も多かったと思います。
運動会、発表会という二つの森フェスは我が子の定点観測のように思える方も多いと思います。毎日毎日お子さまの姿は見ているものの、集団の中で他のこどもに交じって元気に動く姿に1年の成長を感じていただいたことと思います。
私たち大人の社会は評価社会です。様々な私たちの行為そのものが評価されます。それは、金額で評価されるお仕事だけでなく、社会活動や地域活動、しいてはこどもを育てる行為までもが評価され、良い社会人、良い地域人、良い親などと評価されるようなシステムになってしまっています。
このほど新聞で小中の不登校292,000人という記事がありました。私たち乳幼児教育に携わるものにとっても大変ショッキングな数字でした。記事にはコロナ禍で生活リズムが乱れたことも理由の一つだろうと憶測されていました。確かにコロナ禍での3年間は大人でさえ戸惑うことが多い毎日でしたから小さな子たちにはさぞかし大変な混乱の3年間だったろうと思います。
確かに1年生になると登校時間が定められて学校時間が一日の生活リズムの中心になりますね。時間割に定められた生活は、生活リズムがしっかり定められるということになります。
学童期のみならず、毎日の規則正しい生活リズムは乳幼児期のこどもの育ちにもとても大切なことです。こども園の登園時間は午前7時から9時までと2時間の幅があり、大人の生活時間に合わせて園を利用していただいています。朝食をとる時間も一人ひとり違いますからランチの時間も、それに合わせて前後しています。午睡或いは午後の休憩の後、おやつを食べると、それから午後7時まで、およそ4時間の降園が始まります。
毎日が、大人の生活時間に合わせた生活リズムなのですから大人が規則的な生活を志していただくことで子どもたちの生活リズムも安定します。
園にいるときは不安定だったけれど、小学校へ行ったら次第に落ち着いてきたという話を聞きます。もちろん年齢による成長もあるのでしょうが、「登校時間が決められることで、生活リズムが安定してきたということもあるのではないか」とは専門家の意見です。
実りの秋を迎えて、サクラの稲刈りも終わりました。脱穀、精米と、実りを味わうときまではしばらくあるのでしょうが、どれだけ獲れただろうかとここに評価の物差しはナンセンスです。さらに、こどもたちの心の実りはどうでしょう。
人やモノ、さまざまな出会いを通しての豊かな実りも評価することはできません。
なんでも評価する世の中ですが、こどもの成長はしっかり守ります。