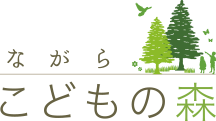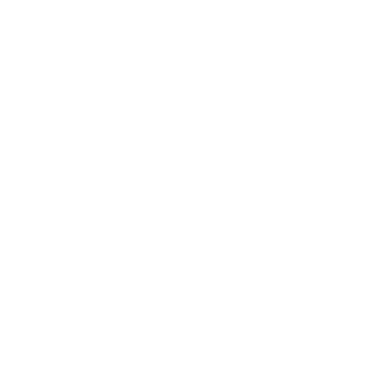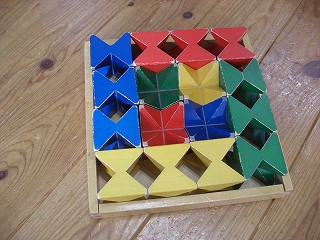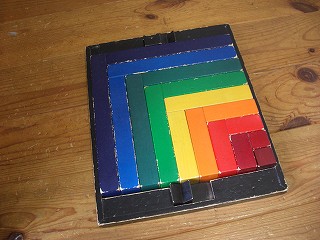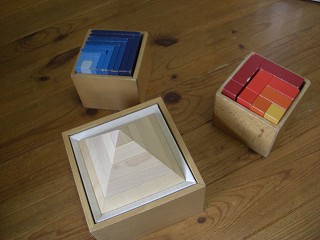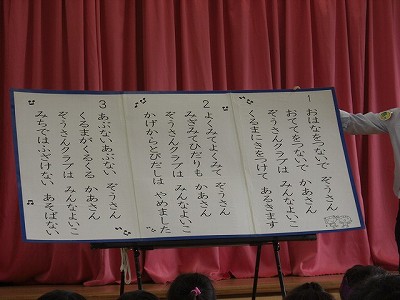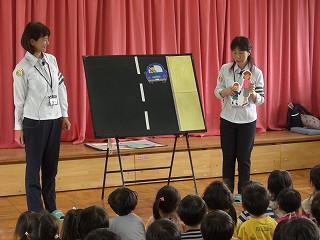2018年11月 森のたより
運動会を終えて、ようやく秋が始まったような気がしています。
さて、今日11月1日は本園での「公開保育」の日です。毎日の保育そのままを県内外の幼稚園、保育園そして認定こども園の先生方に見ていただき、その内容を深めようという催しです。
昨年は乳児3クラスの公開保育をしました。今年は幼児の3クラスを公開します。
今年は「文学」というテーマに取り組んでいます。数年前から教育時間の中で、絵本を読み聞かせることに加えて、お話しを子どもたちに語る「おはなし」の時間を作ってきました。絵本を読み聞かせることが子どもの育ちにどれほど有効であるかは様々なメディアで伝えられ、よく知られているところです。対して「おはなし」はあまり語られてこられなかった分野です。
私自身、母親からお話しを聞いた記憶はありません。但し、祖母からは火鉢の火を火箸で触りながら昔話を聞いたことがあります。この昔話とは「日本昔話」にでてくる「ものがたり話し」でなくて、自分自身が体験したり、村の中でおこった出来事などを語ってくれました。身近な人、身近な場所が登場する話はとても興味深く。何度も聞いたことを思いだします。でも、そんなひとときもテレビの子ども向け時間帯が多くると、次第に無くなっていったように思います。