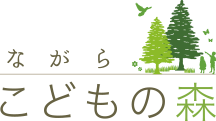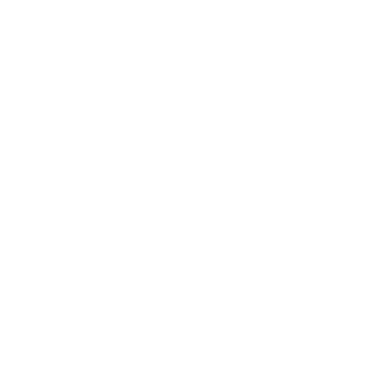2021年11月 森のたより
秋を飛び越えたように寒くなりました。でも園庭の木立を見れば、秋から冬へと移り行く季節の変化を十分に楽しめます。今年も10個を超える柿が実り、干し柿が出来上がりました。先日、たしない干し柿の一片を子どもたちといただきました。ほんとに甘くて、上品な味にびっくりです。カニムカシというお話がありますが、そのお話のようにすくすく大きくなっていっぱい実をつけてほしいと願うのですが、むなしい願いですね。
さて、育児担当制システムのことを続けます。たんぽぽではどの子も二歳の誕生日を迎えます。ハイハイして、ようやくつかまり立ちをしていた1歳のころを思い出せば、ずいぶんと成長し、もう赤ちゃんとは言えませんね。立って歩けるようになると、視界も開け、探索行動も広い範囲となります。イヤイヤと自己主張もするようになって。心も体も随分と大きくなったのです。
この自己主張にも変化があります。○○が欲しいことを泣いたりお母さんの手を引っ張ったりしながら、身体で主張していたのですが、「○○が欲しい」と言葉で表現するようになります。○○が欲しいと求める根底には○○を手に入れた至福の自分が予測できているのです。
この自我の主張をもって「前期幼児教育」ともいうべき歩みが始まっているのです。
「ボクが」「ワタシが」という欲求が成長の姿なのですが、それには「静かにしよう」という大人社会の約束や規範などは一切通じないので大人はどのように接すればよいのかわからずお手上げ状態になってしまいます。
強烈な自己主張ですから、こどもが「イヤ」と言えばやらなくてもいいよと言って、「欲しい」といえば、良いよ良いよと与える。紆余曲折があって結局はこどもの言いなりになったり、或いは交渉が決裂してしまったり。いろいろありますね。でも実はその紆余曲折が大切なのです。それは「いつものことだから」と適当に受け流すのではなく、「受け止める」ということです。「イヤ」の中身、「シタイ」の中身。それをことばで聞きなおし、確認するということですね。
こどもの声より小さな声でゆっくり語りかけるのですが、結構難しいですね。
でも、のれんに腕押し対応でなく受け止めてくれる。これは意思が通じ合うということです。「わかってくれた」という、その心地よさをいっぱい体験することが必要です。
1歳クラスのたんぽぽや2歳児クラスのすみれの担任、そして乳児フリーの2人のスタッフはそのことに多くの時間を費やします。対話するのですね。