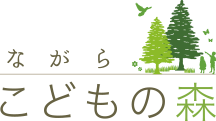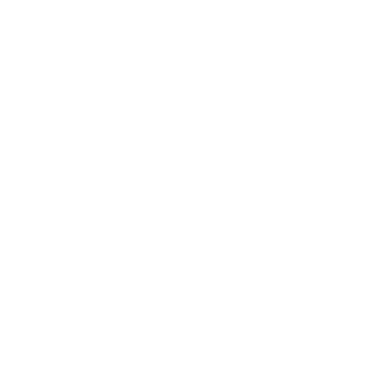2016年8月 森のたより
先月の多子社会と少子社会の続きです。今回は心と体について。
3才、4才と違って大きな子どもたちはハートのマークが大好きです。冬の土粘土遊びではハート型のコップやブローチ、花筒の下絵も赤いハートが描かれます。でも窯の中でもより高温の場所では赤色はほとんど燃えてしまい、残念な結果に終わることもあるのですが、ハートの形に子どもたちは何をイメージするのでしょう。愛情とか、友情でしょうか。いずれにしても「ココロ(心)」の中身?ぼんやりしてるけど大切なモノが思い描かれているように思います。
一方で「カラダ(体)」はどうでしょう。数年前に山梨大学の中村先生は「最近の5歳児の運動能力は25年ほど前の3歳児とほぼ同じ」というショッキングな発表をされました。又NHKでは「広がるロコモティブシンドローム予備群」などと番組をつくり、かなりの確率で子どもの骨や筋肉などの「運動器」に疾患のある恐れがあるなどと伝えています。
多子社会の子育てと少子社会の子育ては同じではダメなようですね。毎日体操の有益さは又後日お伝えしますが、心と体はバランス良く成長発達していかなくてはなりません。